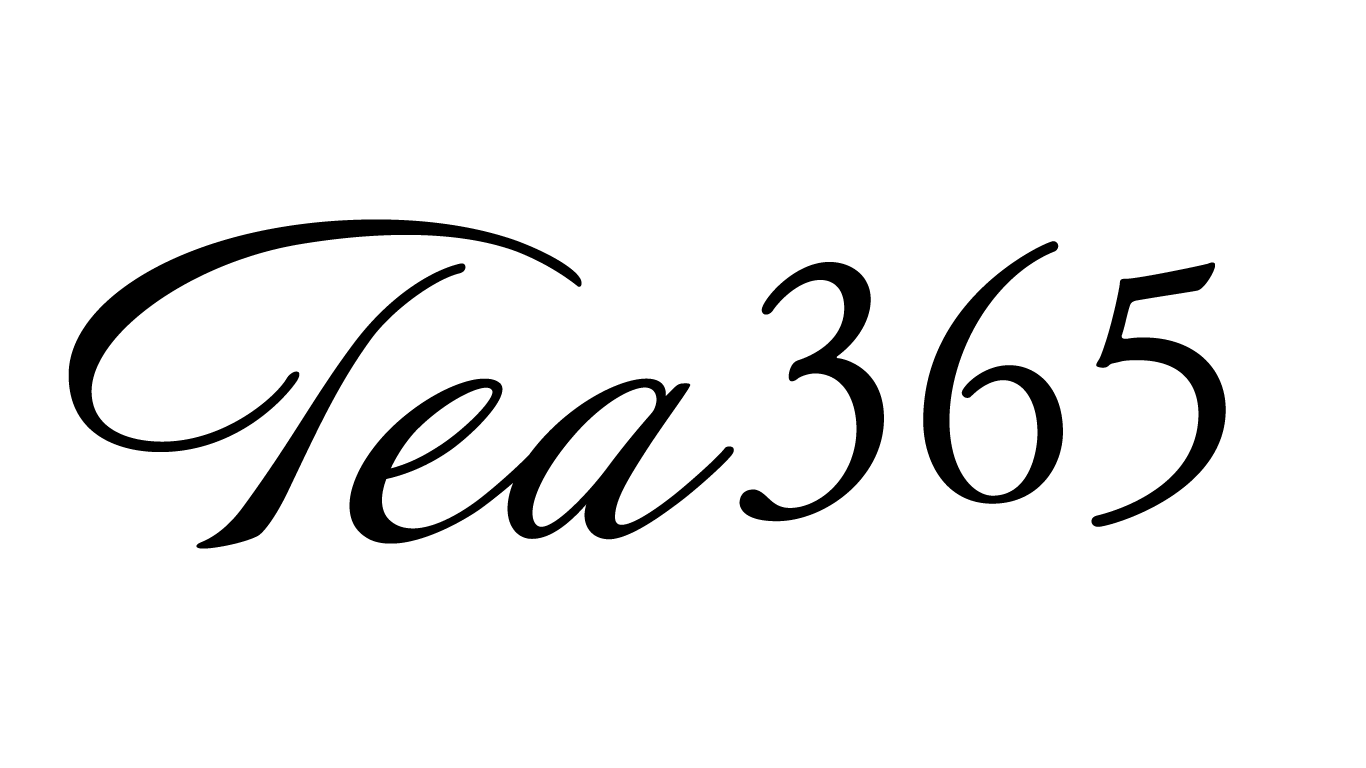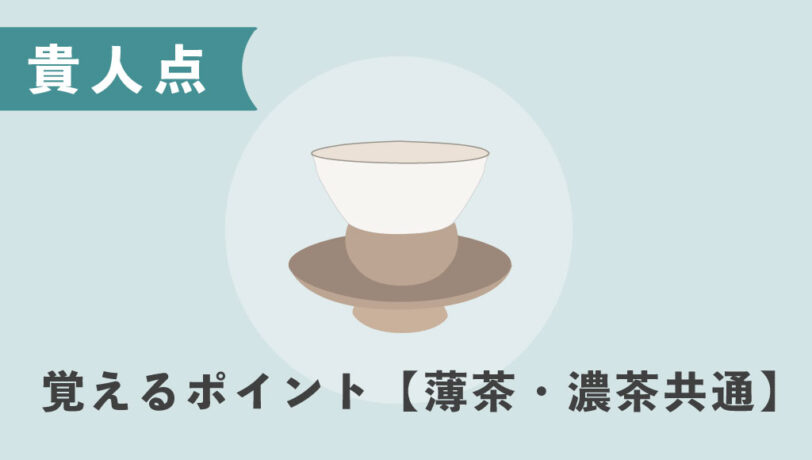貴人点は高貴な方にお茶を差し上げるためのお点前です。薄茶と濃茶とどちらもあります。
高貴な方に差し上げるということは、お点前やお道具もそれに準じたものになります。
 つる
つるどんな厳かなお点前なのだろう・・と警戒してしまいそうですが、ベースとなるのは平点前ですのでご安心ください
こちらのページでは貴人点が通常の平点前と違うところ、どのようなことを意識しておくと覚えやすいかといったポイントをご紹介していきます。
高貴な方に差し上げるためのお点前
はじめにもお伝えした通り、貴人点ては高貴な方へお茶を差し上げるためのお点前です。
では高貴な方とは?と言いますと、昔でしたら身分の高い貴族の方があたります。
現代ですと皇族や元皇族の方などになります。家柄が高貴な方といったイメージでしょうか。
政治家の方や社長さんなどといった偉い方や有名人の方は該当しません。
貴人点で特徴となる動作などはどれもご貴人に対しての恭しさ、敬意を表すためのものです。
お道具などの決まりごと
本来でしたらお茶碗など、新品のお道具を使うのですが、現在ではそこにこだわることは無いそうです。
貴人点ならではのお道具は以下の通りです。
- 貴人台
- 茶碗(貴人台に乗せいやすい天目形のもの)
- 高坏や足つきの縁高
また、このお点前では茶碗や拝見の道具を取り次ぐために半東が控えています。
他のお点前と違うポイント
貴人点で他のお点前と違ってくる点は以下です。
- 貴人台を扱う
- 茶碗は両手扱い
- 茶筅を入れてから茶碗を引く
- お茶を出したら亭主はひと膝下がって控える
- 茶杓を拝見に出す時は帛紗か仕覆の上にのせる
それぞれ確認していきましょう。
貴人台の扱い
高貴な方がお茶を飲むための茶碗は貴人台にのせます。運ぶ際は左手で貴人台の羽を持ち、右手で茶碗を押さえます。
ここでは割愛しますが、いつも手がお道具や壁に当たらないような位置に持ち替えながら持ち上げたり置いたりする。と考えてください。
茶碗は両手扱い
ご貴人の茶碗は両手扱いになります。取る時、置く時は必ず左手を添えて。建水へ湯をあける時には片手でOKです。
茶筅を入れてから茶碗を引く
茶筅通しの際は茶筅を入れてから茶碗を引きます。茶碗が両手扱いのためこうなります。
お茶を出したらひと膝下がって控える
亭主はお茶を点てて定座へ出したらひと膝下がり、両手をついて控えて待ちます。
こ貴人自身が取りに出ることはなく、半東が取り次ぎます。
茶杓を拝見に出す時は帛紗か仕覆の上にのせて出す
茶杓を拝見に出す際、薄茶の時は帛紗の上へ、濃茶の時には仕覆の上へのせて出します。この茶杓は今回新しく用意したもので、ご貴人のためにしか使用していません。なので畳へ直接置かずに大切に扱うのですね。
拝見物も亭主側の人間である半東が取り次がせていただくので、特別に扱うという意味もあるそうです。
質問
- 貴人清次のお点前の時には、茶杓を拝見に出す際に帛紗や仕覆にのせないのはなぜ?
-
貴人清次の場合は、ご貴人だけでなく、お伴の方にも同じ茶杓を使ってお茶を点てます。また、ご貴人の側の人間であるお伴の方が拝見物を取り次ぎますので、へりくだりすぎることはしないそうです。
- 貴人台にのったお茶碗でどう飲んだらいいか分かりません。
-
【薄茶の場合】お茶が出たら貴人台ごと両手で縁内、膝の前に置きます。そこで「お点前頂戴いたします」のご挨拶。
両手で茶碗のみ持ち上げて茶碗を回し、通常通りに飲みます。飲み口を清めたら茶碗の向きを戻し、貴人台の上へのせ、両手で縁外へ置きます。※貴人台を取りこみ、挨拶をしたら貴人台を両手で右膝前に置く という場合もあります(私は正面に置いたままと教わったのですが、教本にはそのように書いてありました)
【濃茶の場合】お茶が出たら貴人台ごと両手で縁内へ取りこみ、右膝の前に置きます。両手で茶碗のみ持ち上げて茶碗を回し、通常通りに飲みます。一口飲んだらご挨拶。
飲み口を清めたら茶碗の向きを戻し、貴人台の上へのせ、両手で縁外へ置きます。 - ご貴人に対してお点前をする機会などないのですが・・
-
実際にご貴人にお茶を差し上げるという機会はそうそう無いかと思います。なので貴人点のお稽古をする必要はないのでは?と私も思ってしまいました。
しかし、実践する機会は無くとも知っておくことが大切です。うやうやしい気持ちでお茶を差し上げるために、どのようなことに気を配っていたのだろう。どんな動作となって表れるのだろう。ということが分かると、お稽古の楽しさも増すかと思います。
まとめ
高貴な方が飲むためのお茶碗が直接畳に乗っているのはいかがなものか。お茶碗や拝見物を取るために動いていただくなど滅相もない。ちょっと極端かもしれませんが、そんな風に考えてみると頭に入りやすいです。